ママと娼婦
劇場公開日:2023年8月18日
- 予告編を見る

解説
ポスト・ヌーベルバーグを代表する夭逝の映画監督ジャン・ユスターシュが1973年に発表した長編デビュー作。
ユスターシュ監督が自身の経験を基に撮りあげた恋愛映画で、1972年のパリを舞台に、五月革命の記憶を引きずる無職の青年アレクサンドルと、一緒に暮らす年上の恋人マリー、アレクサンドルがカフェで出会った性に奔放な看護師ヴェロニカが織りなす奇妙な三角関係の行方を描く。
男女の性的関係を赤裸々につづった内容が物議を醸したが、1973年・第26回カンヌ国際映画祭で審査員特別グランプリを獲得するなど高く評価され、ユスターシュ監督の代表作となった。特集上映「ジャン・ユスターシュ映画祭」(2023年8月18日~、東京・ヒューマントラストシネマ渋谷ほか)にて4Kデジタルリマスター版で上映。
1973年製作/219分/フランス
原題:La maman et la putain
配給:コピアポア・フィルム
劇場公開日:2023年8月18日
その他の公開日:1996年3月23日(日本初公開)
原則として東京で一週間以上の上映が行われた場合に掲載しています。
※映画祭での上映や一部の特集、上映・特別上映、配給会社が主体ではない上映企画等で公開されたものなど掲載されない場合もあります。
スタッフ・キャスト
- 監督
- ジャン・ユスターシュ
- 製作
- ピエール・コトレル
- 脚本
- ジャン・ユスターシュ
- 撮影
- ピエール・ロム
- 編集
- ジャン・ユスターシュ
- デニス・デ・カサビアンカ
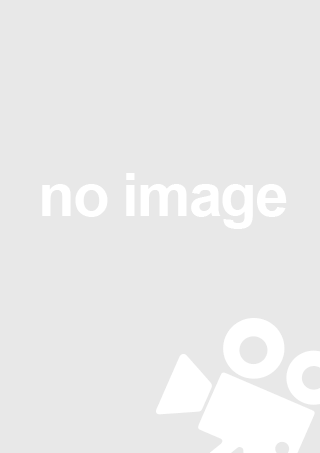


 大人は判ってくれない
大人は判ってくれない 恋のエチュード
恋のエチュード 夜霧の恋人たち
夜霧の恋人たち あこがれ
あこがれ 家庭
家庭 私のように美しい娘
私のように美しい娘 逃げ去る恋
逃げ去る恋 コントラクト・キラー
コントラクト・キラー ゴダールの探偵
ゴダールの探偵 イルマ・ヴェップ
イルマ・ヴェップ
















![ママと娼婦【4Kレストア版】Blu-ray[Blu-ray/ブルーレイ]](https://m.media-amazon.com/images/I/41qssS0jOvL._SL160_.jpg)
![ジャン・ユスターシュ ニューマスターBlu-ray BOX[Blu-ray/ブルーレイ]](https://m.media-amazon.com/images/I/41LYbID32SL._SL160_.jpg)
![ゴールドパピヨン HDリマスター版【スペシャルプライス】ブルーレイ[Blu-ray/ブルーレイ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51cKzpJnYkL._SL160_.jpg)
![プレミアムプライス版 ディンゴ UHDマスター版 blu-ray...[Blu-ray/ブルーレイ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nzss15lCL._SL160_.jpg)
![プレミアムプライス版 ディンゴ UHDマスター版《数量限定版》[DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51YJlMEqXSL._SL160_.jpg)






